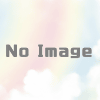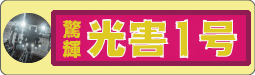食品安全委員会レシピで鶏ハム作った→おおお!市販品のようなやわらかさ

みなさん、ご存じですか?食品安全委員会。
悦にひたって説明しようと思ったら、あっしも正確なところよく分かってないや、ってことに気づきまして、ちゃんと調べてきましたよ、インターネットでチャチャチャと。ええとね。食品安全に関して科学的知見に基づき客観的かつ中立公正にリスク評価を行う機関、ですって。わからー――ーん。まあね、「健康食品って安全なの?」「食中毒ってどうやったら防げるの?」みたいなことを取り扱う国の機関です。たぶん。
となるとですね、食中毒に関することなら、プロ中のプロってわけです。
最近、なんとなく、病院の皆さんって忙しそうじゃないですか。こんなときに、自作の鶏ハム食って、万が一食中毒とかなったら多大な迷惑かけちゃう……。違うの、違うの。この発熱はカンピロバクターなの。って、言い訳も通りそうにない。なんて考え始めちゃって、このところ、あんまり作っていなかったんです。
と、こ、ろ、が。
食品安全委員会が、鶏ハムの作り方動画を出してる――――!
ってことに気がついてしまって。いやいや、プロが教える方法なら、食中毒とかないべ(※)。ってことで、さっそく作ってみました。そしたら、ものすごい市販品に似た口当たりの鶏ハムができちゃいました!!では、作り方を紹介しますよー。
(※)ゼロリスクってことはないそうです。
食品安全委員会の動画はこちらです
レシピ動画というより、実験結果を解説したものです。安全性を考慮したさまざまな調理法について、官能評価をして、ベストな調理方法を導き出しています。
鶏ハムは、中心温度が70℃になるまで湯せんして、5分保持することが大事です。これでカンピロバクターさんがサヨナラできます。
実験では、鶏むね肉約120グラム(6×12×2センチ)を真空包装し、70℃で湯せんした場合、中心温度が70℃になるまでに37.5分かかりました。
ってことを参考にして、作っていきましょう。
鶏むね肉を食品保存袋に入れて、70℃のお湯に浸す
食品保存袋に調味料と鶏むね肉を入れます。それを70℃に沸かしたお湯に入れます。
食品保存袋は、100℃になっても大丈夫なアイラップを使っています。鶏むね肉は120グラム前後にしました。

肉にぶっささっているのは温度計です。なんだよ、温度計いるのかよ、と思ったそこのあなた。そうですよ。内部温度70℃っていわれましてもね、やっぱり測らないと分からないですよ。私が使っているのは「サーモプロ」ってヤツですけど、買って2年で挙動がおかしくなってきているので、そんな、おすすめとかじゃないです。
ひたすら70℃を維持する
お湯の温度は70℃を維持します。っていうか、73℃とかにしておいて、下がってきたらちょっと火を入れて…みたいにしました。

20分後、肉の温度が、70℃に到達―!
37.5分よりも明らかに時間が短いのは「やっべ、80℃になってた」とか、そういう事件がたびたびあったからではないかと推測されます。

で、こっから5分放置すれば完成なわけですが、うん、気づいたら10分経ってた。あはー。
できたよー
できたものが、こちらです。


※まな板が汚くてゴメンナサイ。
いい感じじゃないですかー。ちゃんと火が入っている感もあります。さあさ、実食へ。
ほどよくジューシーで、やわらかーい
いやいやいやいや。おいしいっす。最高っす。
ギリのところでパサついてない感じです。やわらかくて、市販品と同じような食感で驚きました。業者さんもこの条件で作ってるんですかね。

あとは、調味料を工夫すれば、セブン再現がいけそうな気がしてきました。って、最近、セブンのサラダチキン的なもの、まったく買ったことないんですけど、あたしの記憶の中にあるサラダチキンあってんのかな。おいしければ、ま、いっか。ってなわけで、ここまで、読んでいただき、ありがとうございましたー!
食品安全委員会の動画、なんと、ひき肉編も出てるんです。ハンバーグですよ、ハンバーグ。食品安全委員会推奨ハンバーグ。近いうちに、こちらも試してみようかなーって思ってます。ぜひ、また、当ブログに遊びに来てください。
ワッホイ、ワッホイ。